契約書カテゴリーから探す
業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約
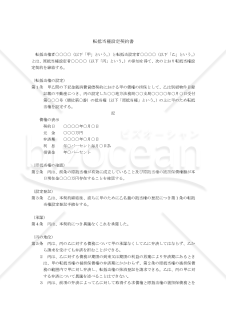
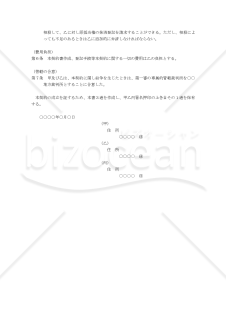




「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)



本「【改正民法対応版】クラウドストレージサービス契約書」は、クラウドストレージサービスを提供する事業者と、そのサービスを利用する企業との間の契約書の雛型です。 本契約書雛型は、クラウドストレージサービスに特有の重要な規定を網羅的に整備しています。 特に、データの管理やセキュリティ対策、障害対応、サービスレベル保証など、クラウドストレージサービスに不可欠な要素を詳細に規定しています。 料金体系を定める料金表、サービス品質を保証するSLA、プライバシーポリシーを別紙として完備しており、実務ですぐに活用できる内容となっています。 本契約書雛型は、主にデータストレージに特化したクラウドサービスを提供する場合に適しています。 例えば、企業向けのオンラインストレージサービス、バックアップサービス、データアーカイブサービスなどを提供する際に利用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(契約の成立) 第4条(サービスの提供) 第5条(利用環境の整備) 第6条(アカウントの管理) 第7条(利用料金) 第8条(サービスレベル) 第9条(計画メンテナンス) 第10条(セキュリティ対策) 第11条(アクセス管理) 第12条(データの取扱い) 第13条(データバックアップ) 第14条(障害対応) 第15条(報告・監査) 第16条(禁止事項) 第17条(一時的な中断) 第18条(サービスの廃止) 第19条(契約期間) 第20条(解除) 第21条(解約) 第22条(契約終了時の措置) 第23条(損害賠償) 第24条(免責) 第25条(不可抗力) 第26条(秘密保持) 第27条(個人情報の取扱い) 第28条(知的財産権) 第29条(権利義務の譲渡禁止) 第30条(反社会的勢力の排除) 第31条(存続条項) 第32条(準拠法) 第33条(管轄裁判所) 第34条(協議解決) 別紙1 料金表 別紙2 サービスレベル合意書(SLA) 別紙3 プライバシーポリシー
■雇用契約書(賃金)の変更のお知らせ(労働条件変更通知書)とは 従業員の賃金や労働条件等に変更が生じた際、その内容を明確に記載し、本人に通知するための文書です。 ■利用するシーン ・昇給や降給、手当の新設・廃止など、賃金体系に変更があった場合に従業員へ通知する際に利用します。 ・労働時間や勤務地、雇用形態など、契約内容に変更が生じた際に、その詳細を明示し通知するために利用します。 ・人事異動や組織再編に伴い、個々の労働条件が変更となる場合に、本人への説明責任を果たすために利用します。 ■利用する目的 ・労働契約法に基づき、変更後の労働条件を明確に伝え、従業員が内容を正しく理解できるようにするために利用します。 ・賃金や労働条件の変更に伴う誤解やトラブルを未然に防止するために利用します。 ・労使間の信頼関係を維持し、公正な労務管理を実現するために利用します。 ■利用するメリット ・労働条件の変更内容が明文化されることで、後の紛争や誤解の防止に役立ちます。 ・従業員に対する説明責任を果たし、企業のコンプライアンス向上につながります。 ・労働者の納得感や安心感を醸成し、職場の信頼関係を強化できます。 こちらのテンプレートは、Wordで作成した雇用契約書(賃金)の変更のお知らせ(労働条件変更通知書)です、ダウンロードは無料なので、従業員の賃金や労働条件を変更した際にご活用ください。
雇用条件や労働法に基づく権利と義務が明確に記載されるもので、雇用者とアルバイトとの合意を明確し、双方が理解する助けとなります。これにより、仕事の期待値や業務内容が明確になり、双方が円滑に協力することが期待されます。 また、信頼関係を築く一助となり、双方が安心して協力できる環境が整います。 雇用契約書は労働法の要件を満たすように構成されるもので、これを確認する手段となります。
所有権保存登記申請書とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記の申請書
賃貸借の対象物件を賃借権譲渡・転貸・増改築したい場合に、賃貸人(大家)の承諾をえるための「賃貸借各種承諾書(賃借権譲渡・転貸・増改築)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
取り扱っている物件の一坪あたりの単価を比較する管理表です。不動産業者、不動産関連業務の方におすすめの書式/テンプレートです。

業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約
請求・注文 社外文書 中国語・中文ビジネス文書・書式 Googleドライブ書式 業種別の書式 リモートワーク 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 売上管理 企画書 契約書 トリセツ その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
