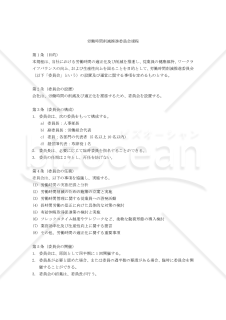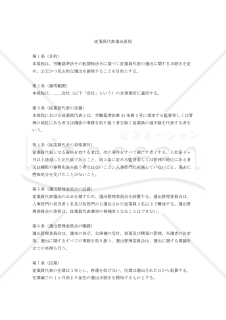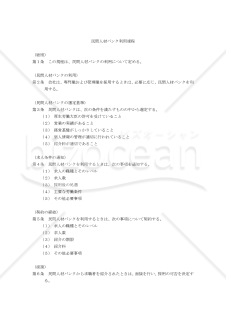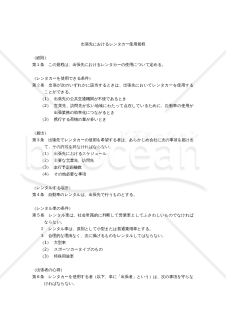(従業員の能力開発、適正配置等の目的のための)自己申告制度規程


「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
労働時間削減推進委員会規程
労働時間削減推進委員会規程
現代の企業経営において、労働時間の適正化は避けては通れない重要課題です。 従業員の健康維持、ワークライフバランスの向上、そして生産性の向上を同時に実現するためには、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。 そのための強力なツールとして、ここに「労働時間削減推進委員会規程」の雛型をご提供いたします。 この規程雛型は、労働時間削減に向けた取り組みを効果的に推進するための委員会の設置と運営に関する包括的なガイドラインです。 目的の明確化から始まり、委員会の構成、具体的な任務、運営方法、さらには他の委員会との連携まで、幅広い内容を網羅しています。 特に注目すべき点として、経営陣の参加を明記し、従業員の意見聴取や情報公開の規定を設けることで、全社一丸となった取り組みを可能にします。 本規程は、大企業から中小企業まで、あらゆる規模の組織に適用可能なように設計されています。 各条項は、企業の実情に合わせて容易にカスタマイズできるよう配慮されており、必要に応じて追加や削除を行うことができます。 この雛型を導入することで、労働時間削減に向けた具体的なアクションプランの策定、実施、評価のサイクルを確立することができます。 さらに、定期的な報告義務や目標設定の規定により、PDCAサイクルを回し続けることが可能となり、持続的な改善を実現します。 労働基準法の改正や働き方改革関連法の施行により、労働時間管理の重要性が増す中、この規程雛型は法令順守の面からも有用なツールとなります。人事担当者や経営者の方々にとって、労働時間削減の取り組みを迅速かつ効果的に開始するための強力な味方となることでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委員会の設置) 第3条(委員会の構成) 第4条(委員会の任務) 第5条(委員会の開催) 第6条(決議) 第7条(報告義務) 第8条(小委員会の設置) 第9条(外部専門家の招聘) 第10条(従業員の意見聴取) 第11条(情報公開) 第12条(目標設定と評価) 第13条(他の委員会等との連携) 第14条(事務局) 第15条(規程の改廃) 附則
従業員代表選出規程
従業員代表選出規程
就業規則の変更や36協定の締結など、労働基準法で定められた従業員の過半数代表者選出。 その手続きが不適切だと労働基準監督署の是正勧告や労使紛争のリスクが高まります。 本テンプレートは「従業員代表選出規程」の雛型です。 この規程雛型は、中小企業から大企業まであらゆる規模の会社で活用できる汎用性の高い内容となっています。 労働基準法に準拠した従業員代表の定義から、選出管理委員会の設置、立候補方法、投票・開票手続き、任期、職務内容まで、必要事項を漏れなく網羅。 特に以下のような場面で効果を発揮します: 「36協定を締結したいが従業員代表をどう選べばいいか分からない」 「就業規則の変更に際して合法的な手続きを踏みたい」 「労働条件の変更について適切な労使協議の土台を作りたい」 「過去の従業員代表選出方法に不備があり、改善したい」 本雛型は明瞭な日本語で書かれており、法律の専門知識がなくても理解しやすく、自社の状況に合わせて簡単にカスタマイズ可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(従業員代表の定義) 第4条(従業員代表の資格要件) 第5条(選出管理委員会の設置) 第6条(選出管理委員会の職務) 第7条(任期) 第8条(欠員の補充) 第9条(選出の告示) 第10条(立候補) 第11条(選挙運動) 第12条(候補者不在の場合の措置) 第13条(投票権) 第14条(投票方法) 第15条(開票及び当選者の決定) 第16条(選出結果の公示) 第17条(従業員代表の職務) 第18条(解任) 第19条(記録の保存) 第20条(規程の改廃)
民間人材バンク利用規程
民間人材バンク利用規程
「民間人材バンク利用規程」とは、企業が従業員の採用や人材の流動化に民間人材バンク(民間の求人・求職情報サービスや人材紹介事業者)を活用する際に遵守すべきルールや手続きを定めた規程です。これにより、企業は効率的に適切な人材を採用したり、従業員がキャリアアップの機会を得られるようになります。 民間人材バンク利用規程を設けることで、企業は人材採用や従業員のキャリア開発において民間人材バンクを効果的に活用できるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(民間人材バンクの利用) 第3条(民間人材バンクの選定基準) 第4条(求人条件の通知) 第5条(契約の締結) 第6条(面接) 第7条(通知)
【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程
【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程
法令順守を含む広義な意味での企業としてのコンプライアンスを定めた社内規程「【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程」の雛型です。 2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ステークホルダーに対する責任) 第3条(投資判断) 第4条(企業倫理) 第5条(意思決定) 第6条(情報管理等) 第7条(健康・安全・環境) 第8条(地域社会) 第9条(公正な取引) 第10条(基本的人権・ハラスメント)
マイナンバー提出書(家族分)・Excel
マイナンバー提出書(家族分)・Excel
本人のほかに、家族や同居人などのマイナンバー(個人番号)を一括して提出する際に役に立つ書類が、こちらのマイナンバー提出書(家族分)です。 マイナンバーのほかに、氏名や生年月日、本人との続柄も記入できるようになっています。 税務署への提出が義務付けられている、法定調書の源泉徴収票や支払調書の作成には、マイナンバーの記載が必要になります。そのため、会社は従業員からマイナンバーを収集しなくてはなりません。 その際には、こちらのExcelで作成したマイナンバー提出書(家族分)をご活用ください。ダウンロードは無料です。
出張先におけるレンタカー使用規程
出張先におけるレンタカー使用規程
本「出張先におけるレンタカー使用規程」は、企業が出張や業務上の移動に利用するためにレンタカーを借りた場合の使用に関するルールを定めた規程の雛型です。 企業が出張や業務上の移動に利用するレンタカーの使用に関するルールを定めることで、事故やトラブルの発生を未然に防止し、安全かつ効率的な業務の遂行を支援することを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(レンタカーを使用できる条件) 第3条(届出) 第4条(レンタルする場所) 第5条(レンタル車の条件) 第6条(出張者の心得) 第7条(日当・宿泊料) 第8条(ガソリン代等の取り扱い) 第9条(費用の前払い) 第10条(実費の請求) 第11条(労働時間の算定) 第12条(事故発生時の対応)

大カテゴリー
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド