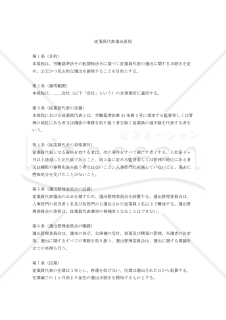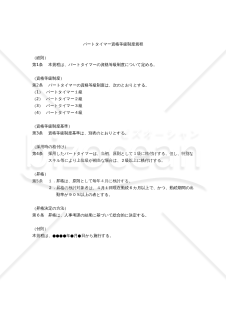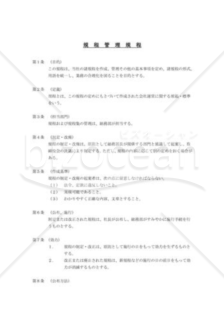【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程
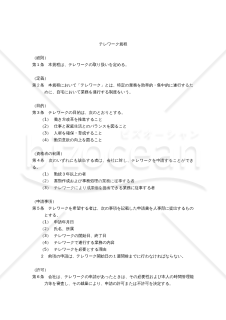

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
従業員代表選出規程
従業員代表選出規程
就業規則の変更や36協定の締結など、労働基準法で定められた従業員の過半数代表者選出。 その手続きが不適切だと労働基準監督署の是正勧告や労使紛争のリスクが高まります。 本テンプレートは「従業員代表選出規程」の雛型です。 この規程雛型は、中小企業から大企業まであらゆる規模の会社で活用できる汎用性の高い内容となっています。 労働基準法に準拠した従業員代表の定義から、選出管理委員会の設置、立候補方法、投票・開票手続き、任期、職務内容まで、必要事項を漏れなく網羅。 特に以下のような場面で効果を発揮します: 「36協定を締結したいが従業員代表をどう選べばいいか分からない」 「就業規則の変更に際して合法的な手続きを踏みたい」 「労働条件の変更について適切な労使協議の土台を作りたい」 「過去の従業員代表選出方法に不備があり、改善したい」 本雛型は明瞭な日本語で書かれており、法律の専門知識がなくても理解しやすく、自社の状況に合わせて簡単にカスタマイズ可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(従業員代表の定義) 第4条(従業員代表の資格要件) 第5条(選出管理委員会の設置) 第6条(選出管理委員会の職務) 第7条(任期) 第8条(欠員の補充) 第9条(選出の告示) 第10条(立候補) 第11条(選挙運動) 第12条(候補者不在の場合の措置) 第13条(投票権) 第14条(投票方法) 第15条(開票及び当選者の決定) 第16条(選出結果の公示) 第17条(従業員代表の職務) 第18条(解任) 第19条(記録の保存) 第20条(規程の改廃)
パートタイマー資格等級制度規程
パートタイマー資格等級制度規程
パートタイマーの採用時及び採用後の資格等級を格付けするための基準を定めた「パートタイマー資格等級制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(資格等級制度) 第3条(資格等級制度基準) 第4条(採用時の格付け) 第5条(昇格) 第6条(昇格決定の方法)
規程管理規程
規程管理規程
会社の諸規程を作成、管理その他の基本事項を定め、諸規程の形式、用語を統一し、業務の合理化を図ることを目的とした規定管理規定のテンプレート書式です。
(規程雛形)個人情報保護方針
(規程雛形)個人情報保護方針
個人情報保護方針の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
苦情処理等ガイドライン
苦情処理等ガイドライン
市民からの苦情等に対し、市の考え方を共有し統一的な取扱いを示すことにより、開かれた市政の推進を図ることを目的とした苦情処理等ガイドラインのテンプレート書式です。
社内文書送付状
社内文書送付状
社内文書送付状のテンプレートです。

大カテゴリー
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド