労務管理カテゴリーから探す
社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 在職証明書 労務安全書類・グリーンファイル 全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 従業員管理 帰化申請

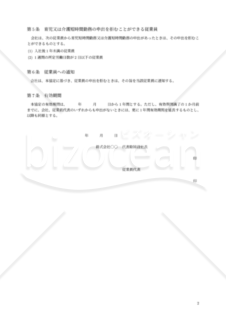



2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。



ユニオン・ショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする労使協定のことを言います。 本書式は、一般的な内容を網羅した「ユニオン・ショップ協定」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(原則) 第2条(非組合員の範囲) 第3条(組合未加入者及び除名者)
嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)
労使協定を結ぶことで、労働者が有給休暇を取得する日を、あらかじめ企業が指定できる制度を「計画年休」と言います。計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限られています。 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年5日の取得義務化されたことで、有給取得率を向上させるために、計画年休の導入が注目されています。 計画年休を導入する際は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」と、書面で労使協定を締結する必要があります。 本書式は、上記のための労使協定である「【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(年次有給休暇の計画的付与) 第2条(大型連休付属休暇日) 第3条(夏季休暇日) 第4条(冬季休暇日) 第5条(対象従業員) 第6条(協議条項) 第7条(有効期間)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類

社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 在職証明書 労務安全書類・グリーンファイル 全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 従業員管理 帰化申請
年末調整 退職・辞職 人事通知・人事通達 勤怠管理 通勤届・通勤手当申請書・通勤交通費申請書 辞令・人事異動 身上異動届・変更届 労務管理 解雇・処分 給与計算・給与管理 社会保険 採用・求人 人事評価・人事考課 休暇届・休暇申請書・休暇願
社内文書・社内書類 中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 業務管理 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
