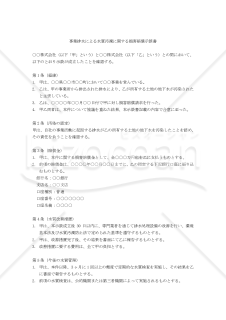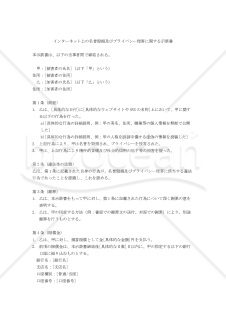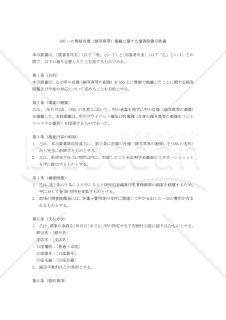【改正民法対応版】飲食店内事故に関する示談書
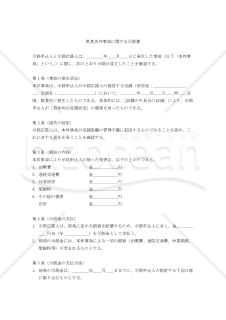

本雛型は、飲食店内における設備の不具合や管理上の問題により、来店客が負傷した場合の示談交渉における合意内容を文書化するための示談書雛型です。 具体的な適用場面としては、椅子や机の破損による転倒事故、天井や壁の設備の落下事故、床の不具合による転倒事故、空調設備の不具合による事故など、店舗設備に起因する事故全般にご利用いただけます。 本示談書雛型は、損害賠償の範囲、支払方法、示談の効力、再発防止策、秘密保持など、実務上必要となる条項を網羅的に盛り込んでおります。 特に、将来的な症状悪化に備えた効力の例外規定や、再発防止に向けた具体的な措置など、被害者と加害者双方の利益に配慮した内容となっております。 また、各条項には具体的な記載例や注意点を示すための括弧書きを設けており、実際の事案に応じて適切な文言を選択いただけるよう工夫を施しております。 なお、本雛型は一般的な事案を想定して作成されておりますので、個別の事案によっては条項の追加や修正が必要となる場合がございます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生状況) 第2条(過失の認定) 第3条(損害の内容) 第4条(示談金の支払) 第5条(示談金の支払方法) 第6条(今後の治療) 第7条(示談の効力) 第8条(再発防止) 第9条(秘密保持) 第10条(協議解決)
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
刑事事件示談書(強制わいせつ等)
刑事事件示談書(強制わいせつ等)
刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書
インターネット上の名誉毀損行為に関する示談書
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書
事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書
インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書
デジタル時代において、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害は深刻な問題となっています。 被害者と加害者の間で適切な解決を図るためには、明確で包括的な示談書が不可欠です。 本「インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書雛型」は、このような現代的な課題に対応するために作成された雛型です。 本雛型は、インターネット上のトラブルに特化した条項を網羅しています。 具体的には、違法行為の明確な定義、謝罪の方法、金銭的賠償、投稿の削除や訂正、再発防止策、さらには守秘義務や紛争解決手段まで幅広い内容を盛り込んでいます。 特筆すべきは、本雛型が単なる一般的な文言の羅列ではなく、実際の使用を想定した実用的な構成となっている点です。 各条項には具体的な行動指針や時間枠が示されており、当事者双方が明確に理解し、遵守すべき事項が詳細に記載されています。 また、将来的な問題を予防するための条項も含まれており、長期的な解決を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(違法性の認識) 第3条(謝罪) 第4条(賠償金) 第5条(投稿の削除及び訂正) 第6条(再発防止) 第7条(甲の権利留保) 第8条(守秘義務) 第9条(紛争解決) 第10条(示談の成立)
【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書
【改正民法対応版】SNSへの無断肖像(顔写真等)掲載に関する損害賠償示談書
この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
示談書06(物損事故B)
示談書06(物損事故B)
物損事故の場合の示談書のテンプレートです。

大カテゴリー
カテゴリーから探す
社内文書・社内書類 中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 業務管理 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド