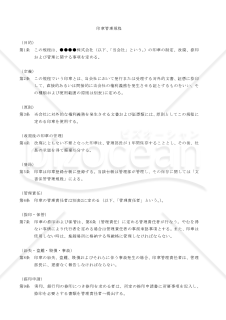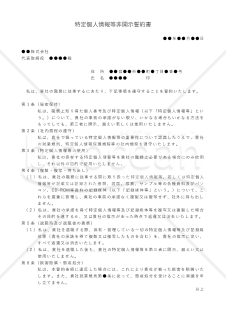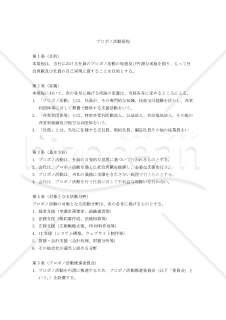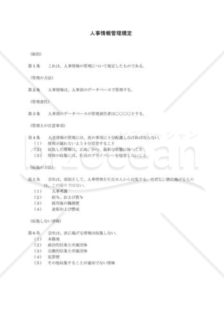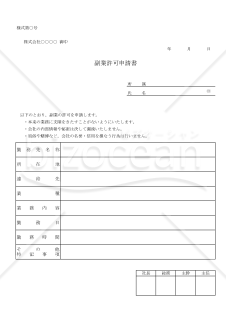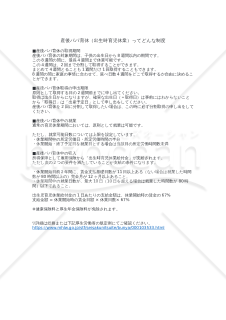地震対策規程
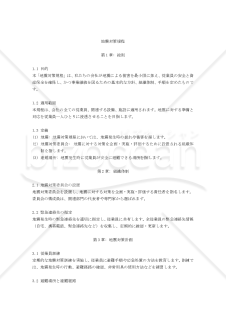
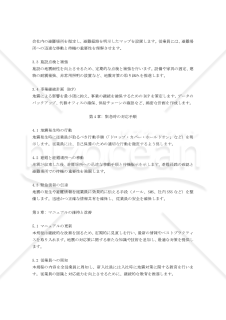




地震対策規程:従業員と資産の安全を確保する手引き 地震は予測が難しく、突然発生する自然災害です。私たちの会社は、地震による被害を最小限に抑え、従業員の安全と資産の保全を確保し、事業の継続性を確保するための基本的な指針と手順をまとめた「地震対策規程」を提供しています。 この規程は、従業員一人ひとりの安全を守ると同時に、組織全体の危機対応力を向上させるために設計されました。以下に規程の主な特徴をご紹介します。 従業員の安全と教育 規程は、地震発生時の適切な行動や避難手順、応急処置の方法など、従業員が緊急事態に備えて必要な知識を提供します。定期的な訓練を通じて、従業員の自己保護能力を向上させるとともに、冷静な判断と行動を促進します。 組織体制と委員会の役割 地震対策委員会の設置により、地震に対する計画的な対策と対応を確保します。専門知識を持つ委員が地震リスクの評価や対策の実施を担当し、組織全体での協力体制を構築します。 避難場所と避難経路の明示 避難場所と避難経路を明確に指定し、従業員が安全に避難できる環境を整備します。適切なマップや案内を提供することで、従業員が迅速に避難し、待機できるようサポートします。 施設点検と事業継続計画 施設の地震耐性を向上させるための定期的な点検と補強、また事業継続計画の策定を通じて、地震の影響を最小限に抑え、迅速な復旧を図るための取り組みを行います。 緊急情報の効果的な伝達 地震発生時の緊急情報を効果的に従業員に伝えるための手段を整備します。リアルタイムの情報共有により、従業員の安全を確保し、的確な対応を支援します。 「地震対策規程」は、従業員の安全と組織の持続的な運営を重視する企業にとって貴重なツールです。ぜひこの規程をご活用いただき、地震リスクに対する適切な準備と対策を推進してください。 〔条文タイトル〕 第1章: 総則 第2章: 組織体制 第3章: 地震対策計画 第4章: 緊急時の対応手順 第5章: マニュアルの維持と改善 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
印章管理規程
印章管理規程
「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)
【マイナンバー対応】特定個人情報等非開示誓約書
【マイナンバー対応】特定個人情報等非開示誓約書
特定個人情報等非開示誓約書は、日本のマイナンバー制度に関連して使用される文書です。マイナンバーは、個人を識別するための一意の番号であり、社会保障や税金などの行政手続きに使用されます。 特定個人情報等非開示誓約書は、マイナンバーを取り扱う機関や事業者、関係者が個人情報の適切な取り扱いを確保するために使用されます。これにより、個人情報の漏洩や悪用を防ぐための規制や監査が行われ、情報の安全性が確保されることを目的としています。
プロボノ活動規程
プロボノ活動規程
本「プロボノ活動規程」は、企業における社員のプロボノ活動を適切に管理・推進するための規程雛型です。 近年、企業の社会的責任(CSR)や社会的価値の創造(CSV)への注目が高まる中、社員の専門性を活かした社会貢献活動であるプロボノ活動の重要性が増しています。本規程雛型は、そうした時代のニーズに応える内容となっています。 特に、プロボノ活動の定義から実施体制、具体的な運用方法、さらには知的財産権や個人情報の取り扱いまで、実務的な観点から必要となる事項を漏れなく規定しています。 活動時間や費用負担、報告義務などについても具体的な基準を示しており、実際の運用がイメージしやすい内容となっています。 本規程雛型は、規模や業態に応じて必要な修正を加えることで、幅広い企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 ・新たにプロボノ活動制度を導入する企業 ・既存のプロボノ活動制度を体系的に整備したい企業 ・社員の社会貢献活動を促進したい企業 ・CSR活動の一環としてプロボノ制度を検討している企業 ・人材育成策の一つとしてプロボノ活動を考えている企業 本規程雛型の特徴は、委員会による全社的な推進体制の構築、具体的な活動分野の明示、明確な手続きの規定にあります。 また、社員の自発的な活動を促しながらも、会社の業務との調和を図る視点も織り込まれています。 さらに、表彰制度や教育研修の規定を設けることで、活動の活性化や質の向上も企図しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(対象となる活動分野) 第5条(プロボノ活動推進委員会) 第6条(事務局) 第7条(登録) 第8条(活動の申請) 第9条(活動時間) 第10条(費用) 第11条(活動の制限) 第12条(報告義務) 第13条(活動の評価) 第14条(表彰) 第15条(保険) 第16条(守秘義務) 第17条(個人情報の取扱い) 第18条(知的財産権) 第19条(免責) 第20条(教育研修) 第21条(改廃)
人事情報管理規程
人事情報管理規程
ありとあらゆる人事情報の取り扱い・管理について規定される。また収集の方法についても記載された人事情報管理規定のテンプレート書式。ワード形式にて作成されています。
副業申請書
副業申請書
Excel書式の副業申請書です。 簡単な約束事と会社名や勤務日などが記載できるようになっています。 都度、変更しながらご自由にお使いください。
産後パパ育休(出生時育児休業)はどんな制度
産後パパ育休(出生時育児休業)はどんな制度
産後パパ育休(出生時育児休業)について記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。産後パパ育休(出生時育児休業)の取得期間や申出期限、就業、収入について細かく記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。

大カテゴリー
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド