労務管理カテゴリーから探す
社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 在職証明書 労務安全書類・グリーンファイル 全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 従業員管理 帰化申請
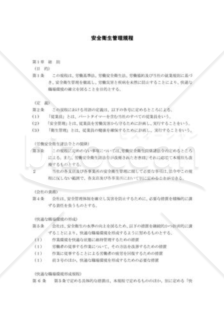

快適な職場環境の確立を図ることを目的として定めた規程



この「寄付に関する社内規程」は、企業が寄付活動を行う際に必要となる重要な社内ルールを定めた雛型です。 会社として寄付を実施する場合、単に善意で行うだけでは十分ではありません。 適切な手続きや承認プロセス、税務処理など、様々な観点から整備された仕組みが必要となります。 近年、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まる中、多くの会社が地域貢献や災害支援、教育支援などの寄付活動に積極的に取り組んでいます。 しかし、寄付活動を行う際には、会社の資金を適切に管理し、透明性を保ちながら実施することが求められます。 また、政治団体や宗教団体への寄付、反社会的勢力との関係を避けるなど、リスク管理の観点からも明確なルールが必要です。 この規程は、Word形式で提供されており、完全に編集可能な状態となっています。そのため、各企業の規模や業種、経営方針に合わせて内容をカスタマイズすることができます。 承認権限の金額設定や寄付対象の分野、申請手続きの詳細など、実際の運用に即した形で調整していただけます。 実際の使用場面としては、新しく寄付制度を導入する企業、既存の寄付活動を体系化したい企業、コンプライアンス体制を強化したい企業などが考えられます。特に、上場企業や一定規模以上の企業では、株主や社会からの説明責任を果たすためにも、このような規程の整備が重要になってきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(寄付対象) 第5条(寄付対象の例) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続き) 第8条(事前調査) 第9条(寄付の実行) 第10条(報告・記録) 第11条(税務処理) 第12条(公表) 第13条(禁止事項) 第14条(監査) 第15条(改廃) 第16条(施行)
OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)
本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)
法令や会社の定款・就業規則等の社内規程に違反した、または違反の疑いのある行為を調査する際の手順・基準を定めた「不正行為調査規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(調査委員会) 第3条(委員の指名) 第4条(委員会の開催招集) 第5条(事実関係の調査) 第6条(調査の方法) 第7条(調査に際しての留意事項) 第8条(調査への協力義務) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(専門家の協力) 第11条(調査結果の報告) 第12条(懲戒処分等) 第13条(再発防止策の提言)
社宅・寮管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に必要な書類です。提出の理由や手順、期限などが明記されます。 マイナンバーの提出が必要な理由などを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらい、提出に同意しない場合の代替手段などを記入することで、個人の意思や権利を尊重することが主な目的です。 こちらは、シンプルなレイアウトのマイナンバー提出依頼書です。必要な項目を入力するだけで、簡単に提出依頼書を作成することができます。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 在職証明書 労務安全書類・グリーンファイル 全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務申請書・労務届出書 従業員管理 帰化申請
年末調整 勤怠管理 退職・辞職 人事通知・人事通達 通勤届・通勤手当申請書・通勤交通費申請書 辞令・人事異動 身上異動届・変更届 労務管理 解雇・処分 給与計算・給与管理 社会保険 採用・求人 人事評価・人事考課 休暇届・休暇申請書・休暇願
マーケティング 社外文書 企画書 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 Googleドライブ書式 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 売上管理 トリセツ 契約書 中国語・中文ビジネス文書・書式 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
