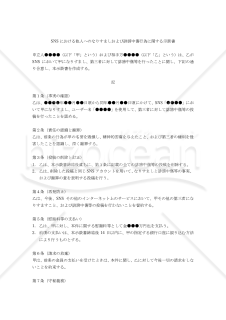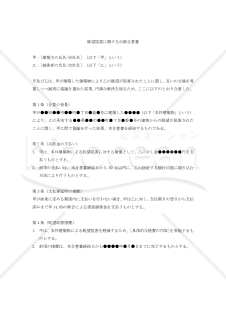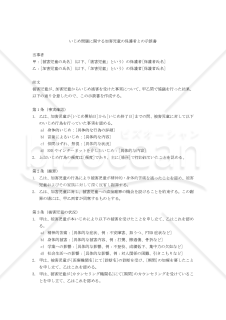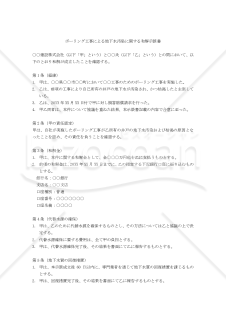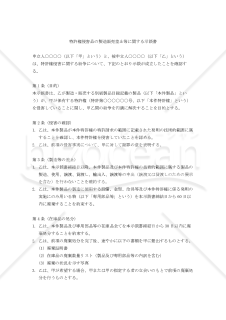著作権法上の翻案権侵害に関する示談書
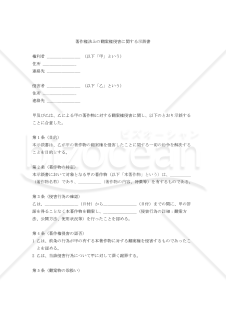

この示談書雛型は、著作権法上の翻案権侵害事案に特化した文書です。 著作者の権利が侵害された際に、訴訟に至る前の段階で当事者間の紛争を円満に解決するための完全な合意内容を網羅しています。 本雛型は、書籍、音楽、映像、イラスト、プログラムコードなど、あらゆる著作物の翻案権侵害ケースに適用可能です。 特にクリエイティブ業界や出版業界、Web制作会社、フリーランスの著作者などが権利侵害を受けた際に活用できます。 また、大学や研究機関、法務部門を持つ企業などが自社の権利保護のために利用することも想定されています。 文書内容は法的観点から精査されており、侵害の認定から賠償、再発防止措置、秘密保持義務に至るまで、著作権紛争解決に必要な要素を20条にわたり詳細に規定しています。 特に翻案物の取扱い、損害賠償、違約金、再発防止措置などの条項は実務的な視点から作成されており、権利者の保護と侵害者の改善を促す内容となっています。 また、本雛型は当事者間の対話を促進し、訴訟コストを回避しながらも権利者の正当な利益を確保することを目指しています。 権利侵害の事実を明確にしつつ、将来に向けた建設的な関係構築も視野に入れた内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(著作物の特定) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(著作権侵害の認否) 第5条(翻案物の取扱い) 第6条(損害賠償) 第7条(遅延損害金) 第8条(権利不存在の不主張) 第9条(甲による法的手続の不開始) 第10条(今後の権利侵害の禁止) 第11条(違約金) 第12条(再発防止措置) 第13条(権利処理の方法) 第14条(公表に関する合意) 第15条(秘密保持義務) 第16条(権利非譲渡) 第17条(完全合意) 第18条(本示談書の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄)
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書
SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書
本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
【改正民法対応版】(建築物の建築による)眺望阻害に関する示談合意書
【改正民法対応版】(建築物の建築による)眺望阻害に関する示談合意書
本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書
いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書
本「いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書」は、いじめ問題の解決を目指す保護者や関係者にとって、重要な指針となる雛型です。 本雛型は、いじめ事案の事実確認から始まり、謝罪、被害状況の詳細な記録、再発防止策、被害児童への継続的支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 特筆すべきは、この雛型が単なる法的文書の枠を超え、教育的観点も重視している点です。 加害児童に対する具体的な教育的措置や、被害児童の回復に向けた長期的なサポート計画が明確に示されており、問題の根本的な解決を目指す姿勢が表れています。 また、学校との連携や経過観察の仕組みを組み込むことで、継続的な改善と再発防止を図っています。 本雛型は、秘密保持や誹謗中傷の禁止など、現代社会特有の課題にも対応しており、SNSを含むデジタル時代のいじめ問題にも適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(被害児童の状況) 第4条(再発防止と教育的措置) 第5条(被害児童に対する今後の対応) 第6条(学校との連携) 第7条(損害賠償) 第8条(今後の経過観察) 第9条(秘密保持) 第10条(誹謗中傷の禁止) 第11条(解除条件) 第12条(紛争の解決)
ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書
ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書
特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
示談書04(人身事故C)
示談書04(人身事故C)
人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。

大カテゴリー
カテゴリーから探す
請求・注文 社外文書 中国語・中文ビジネス文書・書式 Googleドライブ書式 業種別の書式 リモートワーク 経営・監査書式 コロナウイルス感染症対策 業務管理 売上管理 企画書 契約書 トリセツ その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド