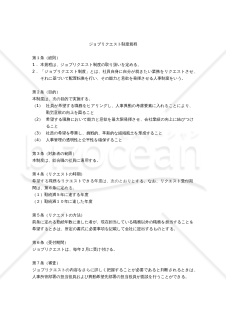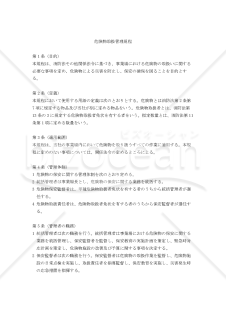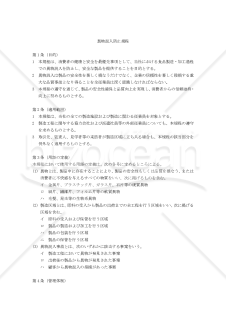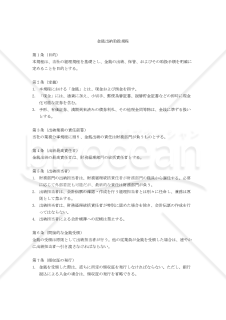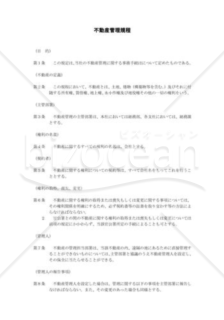管理職任期制規程


「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
ジョブリクエスト制度規程
ジョブリクエスト制度規程
「ジョブリクエスト制度」とは、社員自身に自分が就きたい業務をリクエストさせ、それに基づいて配置転換を行い、その能力と意欲を発揮させる人事制度をいいます。 本書式は、ジョブリクエスト制度の運用について定めた社内規程の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(リクエストの時期) 第5条(リクエストの方法) 第6条(受付期間) 第7条(審査) 第8条(発令日) 第9条(人事異動の見送り)
危険物取扱管理規程
危険物取扱管理規程
本規程は、消防法で定める危険物および事業場独自で定める危険物を取り扱う事業場向けの管理規程の雛型となります。 製造業、倉庫業、研究機関、教育機関など、危険物を日常的に取り扱う事業場において、安全かつ適切な危険物管理体制を構築するための基本となる規程です。 本規程では、危険物の取扱いに関する基本的な安全管理体制、作業者の資格要件、具体的な作業基準、施設の点検方法、事故発生時の対応手順など、事業場における危険物管理に必要な事項を体系的に定めています。 特に管理体制については、統括管理者、保安監督者、取扱責任者の役割を明確に規定し、責任の所在を明らかにしています。 また、作業者の資格要件や教育訓練についても詳細に定めることで、確実な安全管理を実現できる内容となっています。 本規程は、消防法その他関係法令に準拠しており、事業場の規模や取扱う危険物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、様々な事業場で活用することができます。 特に、危険物の製造、貯蔵、運搬等を行う事業場や、研究開発部門を持つ事業場において、安全管理体制の構築に役立つ内容となっています。 各事業場における実際の運用に当たっては、取扱う危険物の特性、作業内容、施設・設備の状況等を考慮し、必要に応じて具体的な数値基準の追加や、より詳細な手順の追記を行うことで、より実効性の高い規程として活用することができます。 また、事業場の安全衛生委員会等での審議を経ることで、現場の実態に即した内容に改善することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理者の職務) 第6条(作業者の資格要件) 第7条(取扱作業の基準) 第8条(保護具の使用) 第9条(危険物の保管) 第10条(施設の点検) 第11条(事故時の措置) 第12条(教育訓練) 第13条(記録の管理) 第14条(改廃)
異物混入防止規程
異物混入防止規程
食品製造業における異物混入防止は、企業の信頼性と製品の安全性を確保する上で最も重要な課題の一つです。 本規程雛型は、食品製造現場における異物混入防止のための包括的な管理体制を確立するために必要な要素を網羅的に整理したものです。 本規程雛型では、総括責任者から現場の管理者まで、各階層の責任者の要件と職務を明確に定義しています。 また、製造区域の入室基準から異物検出装置の具体的な管理基準まで、現場で即座に活用できる実践的な基準を提供しています。 特に、金属検出機やX線検査装置については、検出感度や点検頻度など、具体的な数値基準を示しており、そのまま運用に移せる実用的な内容となっています。 さらに、異物混入事故が発生した際の対応手順、記録の管理方法、定期的な監査の実施要領など、PDCAサイクルを確実に回すために必要な要素も織り込んでいます。 本規程雛型の定期的な見直しについても明確に規定しており、継続的な改善を可能にする構成となっています。 本規程雛型は、ISO 22000やHACCPの要求事項にも対応した内容となっており、食品安全マネジメントシステムの構築・運用にもお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(総括責任者の職務) 第6条(製造ライン責任者の職務) 第7条(品質管理責任者の職務) 第8条(衛生管理責任者の職務) 第9条(製造区域の管理基準) 第10条(施設・設備の管理) 第11条(異物検出装置の管理) 第12条(異物混入事故発生時の対応) 第13条(記録の管理) 第14条(監査) 第15条(是正措置) 第16条(規程の見直し) 第17条(補則)
金銭出納取扱規程
金銭出納取扱規程
本「金銭出納取扱規程」は、企業の財務管理における重要な規程雛型です。 本規程雛型は、金銭の出納、保管、および取扱手順を明確に定めることで、組織の財務プロセスの透明性と効率性を高めることを目的としています。 金銭の定義から始まり、出納業務の責任体制、金銭の受領と支払いの手順、小切手や手形の取り扱い、小口現金の管理、印鑑の管理、そして事故発生時の対応まで、幅広くカバーしています。 特に、出納担当者の役割と責任、支払い手続きの詳細、そして内部統制の仕組みについて詳しく規定しており、不正や誤りのリスクを最小限に抑える構成となっています。 本規程雛型は、中小企業から大企業まで、様々な規模の組織に適用可能なように設計されています。各社の特性や要件に合わせて適宜カスタマイズすることで、より効果的な金銭管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出納業務の責任部署) 第4条(出納最高責任者) 第5条(出納担当者) 第6条(間接的な金銭受領) 第7条(領収証の発行) 第8条(入金処理) 第9条(支払いの基本方針) 第10条(支払い要請手続き) 第11条(支払い実行手順) 第12条(前払いおよび仮払い) 第13条(小切手の発行) 第14条(手形発行の禁止) 第15条(手形・小切手の受領処理) 第16条(支払い証憑の取得) 第17条(書損じ・取消し処理) 第18条(残高確認) 第19条(小口現金の管理) 第20条(印鑑の管理) 第21条(事故発生時の対応) 第22条(規程の管理と改定)
不動産管理規程
不動産管理規程
不動産に関する所有権、賃借権、地上権等の権利を明記した不動産管理規程のテンプレート。無料でダウンロードが可能です。
駐車場管理規程
駐車場管理規程
マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定

大カテゴリー
カテゴリーから探す
中国語・中文ビジネス文書・書式 社内文書・社内書類 マーケティング 業務管理 その他(ビジネス向け) 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド