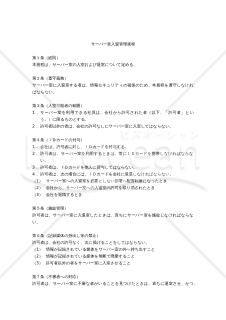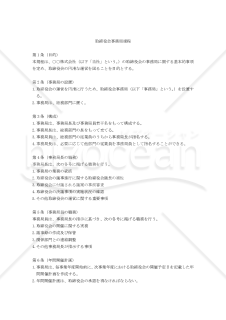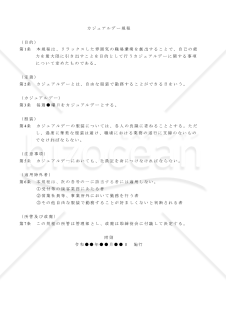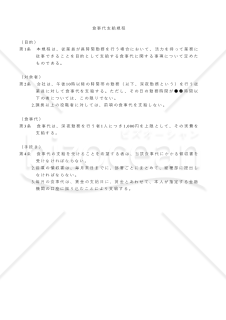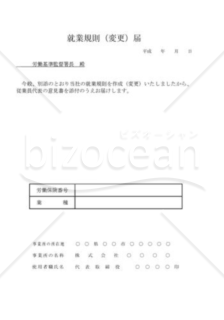【改正労働安全衛生法対応版】ストレスチェック制度実施規程


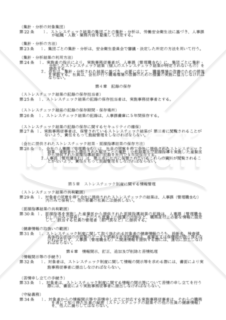




労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
レビューを投稿



プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
サーバー室入退管理規程
サーバー室入退管理規程
サーバーを設置している部屋への入退室はITセキュリティのため厳重に管理をするべきです。 本書式はサーバー室への入退室を管理するルールを定めた「サーバー室入退管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(遵守義務) 第3条(入室可能者の範囲) 第4条(IDカードの付与) 第5条(施錠管理) 第6条(記録媒体の持出し等の禁止) 第7条(不審者への対応) 第8条(持込制限) 第9条(整理整頓) 第10条(火気の取扱い) 第11条(会社への届出)
取締役会事務局規程
取締役会事務局規程
本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)
カジュアルデー規程
カジュアルデー規程
カジュアルデー規程は、企業や組織において従業員に一定の日や期間においてカジュアルな服装や服装規定の緩和を認めるための規定やガイドラインです。 通常、企業や組織は厳密な服装規定を設けており、ビジネスカジュアルや正装など特定のスタイルや規定に従った服装が求められます。しかし、カジュアルデー規程では、特定の日や期間(通常は週末や特定の曜日)において、従業員がよりリラックスした服装で勤務することを許可しています。 カジュアルデー規程は、従業員のモラールやワークライフバランスを向上させるために導入されることがあります。従業員は通常のビジネススーツやフォーマルな服装に比べて快適さを感じることができ、より自由な雰囲気で働くことができます。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(カジュアルデー) 第4条(服装) 第5条(注意事項) 第6条(適用除外者) 第7条(所管及び改廃)
食事代支給規程
食事代支給規程
食事代支給規程は、従業員が長時間勤務を行う場合に、業務への活力を維持するために支給される食事代に関するルールや規定を定めたものです。 この規程は、従業員が労働時間や勤務条件により食事を摂る機会が制限され、業務の遂行や健康維持に支障をきたす可能性がある場合に適用されます。食事代支給規程は、企業や組織が従業員の食事状況に配慮し、業務におけるパフォーマンスや健康の維持を促進するために策定されます。
有期労働契約雇止め理由証明
有期労働契約雇止め理由証明
有期労働契約を更新しない理由を明記し、その理由を証明するための書類
就業規則届・意見書
就業規則届・意見書
就業規則届・意見書とは、就業規則が変更になった場合に届け出る書類

大カテゴリー
カテゴリーから探す
社内文書・社内書類 中国語・中文ビジネス文書・書式 マーケティング 業務管理 経営・監査書式 Googleドライブ書式 契約書 売上管理 コロナウイルス感染症対策 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 企画書 トリセツ 請求・注文 リモートワーク 業種別の書式 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド